2017年度公募研究課題3「視覚文化史における幻燈の位置」
国際シンポジウム
日本のスクリーン・プラクティス再考
視覚文化史における写し絵・錦影絵・幻燈文化
パネルディスカッション
日本のスクリーン・プラクティス再考
草原 フータモさんは池田組の錦影絵を見るのが今回初めて、それから、みんわ座さんの「葛の葉」を見たのも初めてだと思いますので、先ほどの(基調報告で話題になった)Screenology、あるいはスクリーン・メディアとかプロジェクション・メディアの視点から、上演についてコメントをいただけたらと思います。

フータモ ずっと私は日本の伝統的な幻燈機のパフォーマンスに大変魅了されてきました。私は1998年に初めてみんわ座の公演を見たのですが、それまでに西洋のマジックランタンのショーをたくさん見ていました。そのため、共通点もたくさんあるけれども、表現方法など相違点もたくさんあることにすぐに気づきました。
特に日本の写し絵というのは、現代的な表現を使うと、複合的な映像になっています。つまり、それぞれ違うランタン、いくつかの違う風呂(写し絵の投影装置)から投影されている映像が複合して、一つの作品が作られています。それに対して西洋のマジックランタン・ショーは、基本的に静止している映像です。もちろん多少はスライドが動くことはありますけれども、大体一つの映像で一つのことだけが起こっています。これに対し、日本の写し絵では、いくつかのことが同時に起こっています。
なぜ、日本でこのような発展をしたのか、その理由を私はいつも考えています。もしかすると、アジアにもともとあった伝統的な影絵の影響があるのかもしれません。日本の伝統的なストーリーテリングの影響もあったのかもしれませんが、そこに西洋と違う面があります。例えば今日のパフォーマンスを見ても、二種類の違う演じ方がありました。
みんわ座の方は、最初はコミカルな作品でしたし、もう一つの作品はもっとドラマチックでゆっくりとした動きのものでした。また池田組の作品は伝統と新しいもの、過去と現代的なものを組み合わせていたと思います。私の視点から見ますと、伝統的なものと新しいものという、異なる要素を組み合わせる可能性が示されていると思います。
ですから、結論を言うと、日本の映像文化の伝統というのはある意味特殊なものがあると思いますし、少なくとも私が知っている限りでは、他のどの文化とも違う側面があり、それが大変興味深い資産になっていると思います。
草原 どうもありがとうございました。伝統的な題材と、それを使って新しく現在に生かしていくという話だったかと思います。池田先生の方から今のコメントに対してどうですか。なぜ錦影絵というメディアを使って、新しいことに取り組んだのでしょうか。どういう所に興味を持ってこれを始められたのでしょうか。
池田 私も長い間映像の仕事をしてきましたけれど、錦影絵の一番大きな魅力は、身体の動きと映像が密接に繋がっているということです。テクノロジーを使って身体の動きを計算して映像を動かすということは現在でもありますが、ドラマの微妙な感情にまで深く入り込むような、身体と密接に結びついた日本ならではの表現に、驚きと新鮮さを改めて感じて、錦影絵の虜になりました。種板(スライド)の薄い板の間にどれだけ仕掛けを組み込めるか、という知恵比べの側面もありますし、素材をよく知って、工夫して仕掛けを作るというのはまさしくマニファクチャーの基本だと思いますが、それが錦影絵には生きている。それが驚きだけではなく、表現に結びついている。身体と映像とテクノロジー、デバイスが密接に結びついた表現ということになります。それが魅力だと思います。またその表現は日本独特のものでもあるということが、調べれば調べるほど分かってきて、虜になりました。
草原 工夫して種板を作ることだけではなく、それを使って演じることにも色々な可能性があって、それぞれの個性が出るわけですよね。以前、みんわ座さんが持っている種板を見せてもらった時に、同じようなシーンで少しずつポーズが違う画像がたくさん並んでいました。そして、種板と風呂の間に少し隙間があって細かく動かすことができる。たとえば、別れの手紙を受け取って泣いている女性を、細かく種板を震わせて表現するとか。
その辺りの写し絵ならではの表現について、山形さん、いかがですか。写し絵を始めてから発見したこと、工夫したことなどたくさんあると思うのですが。

山形 写し絵をはじめてから、東京都写真美術館で草原先生とお会いして、その後ヨーロッパのマジックランタンについて色々と指導を受けました。ヨーロッパと日本の種板の違いは、 しっかりと絵が動いて、種板が組み合うのが西洋。それに比べて日本の種板は風呂に対して隙間があるんですよね。日本の芸能で言う「遊び」ですよね。つまり、しっかり動いてカチッと止まるのがヨーロッパの種板です。日本の種板は遊びがあるから、泣いたり笑ったりという微妙な動きがそれを使ってできるんですね。それに付随して、例えば、写し絵はレンズの前にあるたった一枚の布が光源を塞いでいて、それを徐々に上げていくことで絵が現れてくる、また下げていくことで徐々に消えていく。ヨーロッパのマジックランタンは金属製だから、絵がすっと消える。そういう微妙な表現ができることが写し絵とマジックランタンの違いとしてある。
そして、池田先生や草原先生と違うのは、私は演じる人間ですから、研究者ではないんですね。なぜ写し絵を始めたかというと、実はもともと(みんわ座は)影絵芝居の劇団でして、透明なプラスチックの板の先に鳥をつけて、それをテグスで引いて(影絵の)鳥を飛ばすということをやっていました。しかし光の屈折の関係で、透明な板と言っても光が当たると微妙に影が写るんです。でも写し絵を使えば、影がなくて済むんですね。そのことを、たまたま偶然にペンタックスの写真年鑑で「200年前に日本で行われていた芸能」というページを見て知って驚いて、その技術が今に伝わっていない、伝わっていたとしても今ではほとんど演じられていない、ということが分かって、それでチャレンジをしました。
当時、写し絵に価値があるとは全く思っていませんでした。というのは、「古いもので価値があるよ」とは色々な人から言われていたけれども、どんな価値があるのか正直よくわかりませんでした。復元するためには、結構お金がかかるんですね。それで、そのためにあちこち助成を申請に行きました。しかし、ものの見事に同じことを言われました。「一度滅んだものは、滅ぶ意味があって滅んだものだから、価値がないんだよ。今更それをやって見てくれる人がいるとあなた思うのですか」という風にずっと言われ続けてきました。
それで、2001年に「イギリスにおける日本文化紹介年」というのがあり、イギリスに行きました。最初に招待してくれたマジックランタン協会で公演した時に、それこそ鳴り止まない拍手をもらいました。日本では考えられないことで、とにかく感動のあまり体が震えて、お礼の言葉が出ないんですね。そのあと(日本文化・美術史研究者の)タイモン・スクリーチさんが招いてくれて、ロンドン大学で公演し、そしてあちこちの教会を回って、最後にブライトンの映画祭に行きましたけれども、映画祭でもそうでした。ヨーロッパの全ての場所でスタンディングオベーションをもらいました。でも日本に帰ってくるとダメなんですね。昔のものになってしまう。なんとか、でも今の時代に活かしたいということを考えて、まずとっかかりとして古典作品をやって、昔日本にこういうものがありました、そういうことを伝えて、その後で改良して現代的なものにチャレンジして行こうと思ってこれまで続けてきました。
たまたま今週の月曜日に、(共同研究メンバーの)向後先生の明星大学で「田能久」という作品を上演しました。これは落語ネタで、元々は四国・徳島の民話です。旅芸人が大蛇に襲われて、田能久(たのきゅう)という名前が大蛇に「たぬき」と聞き間違えられて、狸ならば七化けできるだろうということで、色々な衣装を行李から出してお姫様だったり小坊主だったり、鬼に化けたりといった、コミックな話です。これは仕掛けがあり、現代的で面白い話なんですね。それを向後先生からお声がかかって、今週月曜日に上演を終えたところなんですね。このようにして、古典作品そのままではなく一つのスタイルとして残しながら、それを現代的に受け入れてもらえるような形にしていくことにチャレンジしています。
草原 先ほど山形さんが最初に言われた「遊び」という言葉。日本には遊びの文化があると言われていて、遊びには隙間、空間という意味もあるというのが面白いですよね。それが文化のベースにあって、演じ方にも影響している。
あともう一つ、今はこれだけ人が集まっているから大丈夫だと思うんですが、助成を申請する時に「滅びたものをやってもしょうがない」と言われたということです。これはまさしくフータモさんが「メディア考古学」が重要だと言っていることと繋がると思いますが、いかがでしょう。日本では、古いものが滅びてしまったら仕方ないという考え方があるのでしょうか。なぜ一度滅びてしまった文化とか、あるいは他の発展の仕方があったかもしれないけれども、その時の社会のあり方や技術だと、そこで行き止まりになってしまったテクノロジーとか、そういったものに注目する意味はどこにあるのでしょうか。

フータモ その前に一言、山形さんが西洋で写し絵が非常によく受け入れられたというお話をされました。ちょうど2001年にみんわ座がイギリスで公演した時に、私はその場所にいました。おそらく、どういうものを見ることができるか誰も知らなかったので、皆とても驚いたと思います。初めて写し絵を見た時、本当にあたかも突如として知らないものが現れたような感じがして、みんな大変驚きました。ですから、同じようにロサンゼルスでも大反響があったのだと思います。ハリウッドの映画産業で最も名声のある劇場で上映されましたけれども、その時もスタンディングオベーションがあって、入場券も売り切れて大変な反響でした。新鮮さと驚きの両方の組み合わせだったと思います。
そして、ご質問の点ですけれども、大変難しい内容で、考えるのにじっくり時間をかけなければいけない問題ですが、過去との関係については、おそらく日本では江戸時代から明治への移行と関係があるのではないかと思います。急激に日本を近代化させようとして明治維新があったわけですけれども、これは短い時間で大変多くのことが達成された極端な変革だったと思います。多くのことが達成されましたが、同時に既存の伝統などが無視されたという代償もあったと思います。
明治時代に日本に招聘された西洋人、例えばラフカディオ・ハーンなどについて書かれたものを読みますと、日本が近代化した道のりについて嘆いているということを、みなさんよく書いています。それは伝統が無視されたということを嘆いているのだと思いますが、そういうことと関係があるかもしれません。つまり、今までの伝統的なものを捨てて忘れてしまうということについて、もしかすると西洋の人たちとは伝統との関わり方が違うのかもしれません。
草原 伝統を今にどう生かすか、という点で言えば、池田さんは大学という場で、毎年入れ替わる学生さんたちと一緒に上演をして、毎年毎年教えている。これは大変なことだと思います。
池田 確かにかなりエネルギーは使います。ただ、私は伝統ということではなくて、一つの表現、表現媒体である、日本独特であるけれども一つの映像表現であると思って関わっています。もちろん、歴史を知れば知るほどすごいなと思うけれども、やっぱりこのメディアが持っている、和紙とか空間の捉え方とか、先ほど言ったデバイスの問題とか、本当に一つの映像表現であり、外国にはない日本に独特の映像メディアということで、学生たちとも関わっていますし、だから頑張っていけるし、古いものという形では考えていないです。
草原 昔あったものというわけではなく、まさに今、新しいメディアとして、ということですよね。
池田 もちろん、古いものだということは知っていますが、このメディア、この媒体の中で何ができるのか、昔の人たちがやってきたことをちゃんと知って、なおかつその上で、それ踏襲しつつ何ができるか。決して打ち破るのではなく、踏襲して何ができるのかということだと思うんです。
草原 そういう面で言うと、私が山形さんたちにお会いして、びっくりしたのは、そもそも雑誌に写し絵の特集があったからといって、それをやってみる人ってなかなかいないですよね。何度も研究者ではないとは仰っていましたけど、本当に色々研究されている。
私は、80年代はコンピュータグラフィックスの専門家だったんですけれども、ここにはないものをどうやって表現するかということに興味があった。その延長で写し絵に関心を持ちました。その時驚いたのは、もともと山形さんたちが種板もないところからはじめて、パソコンというものを使ったら種板が作れるらしい、ということを言って、パソコンが非常に高価だった時代にそれを借りてきて、イラストレーターのソフトを使って、浮世絵の色々なパーツを組み合わせて画像を作った。そのチャレンジ精神がすごいなと思ったんです。古典的な昔あったものを残そうというだけではなくて、どうやって今の技術を使ったり、今の映像表現を使って組み合わせていくか、ということだと思います。
池田 そういう意味では、確かに和紙のスクリーンには和紙のスクリーンの特徴があって、影に厚みが出るんですね。影に存在感があって、それが動くという特性がある。今、イラストレーターで絵を作ったという話がありました。私は光源実験をしていて、好奇心があるので、昔は本当に灯芯、燈明で錦影絵の映像が見えたのだろうか、というのが不思議だったので、実際に灯芯を買ってきて、菜種油で写してみて、ああやっぱり見えたんだ、ということが分かった。次に蝋燭でやってみた、やっぱり見えた、蝋燭で煤だらけになったけれども、決して桐(の投影装置)は燃えなかったということも確認できた。石油ランプも煤だらけになったけれども、この明るさでちゃんと映ることが分かった。だから昔の人達は燈明で錦影絵を楽しむことができた、という確信がある。そういうことを積み重ねて、その延長で今の技術ということで LED を使ったら、コマ収差ができて全然使い物にならなかった。やっぱり昔の光源、今日みんわ座さんが使った白熱灯とか、ハロゲンとか、それが今の段階ではベストだよね、ということになったり。昔のことを大事にしながら一つ一つやってきて、今の物を使ってみるという事をしている。うちの場合は大きなライトは使えないので、バッテリーで動けるようにするにはどうしたらいいか考えて、1年以上かけて今のシステムになった。パソコンを崩して(冷却用の)ファンを風呂に入れたりとか、いろんな工夫をして、今できることでやっています。でも絶対に(素材は)桐で、和紙でということは崩さない、ということは守っています。
草原 伝統的な事をやっているだけではなくて、実は背後にはいろいろ工夫がある。
山形 もともと私は芝居屋なんで、研究者ではないんです。どういう風な演出で使えるかということがいつも関心にあります。写し絵の特徴は、手動で映像を操作できることの魅力なんですね。一度、会場の電気を消してもらえますか。(会場の壁に写し絵を投影する)
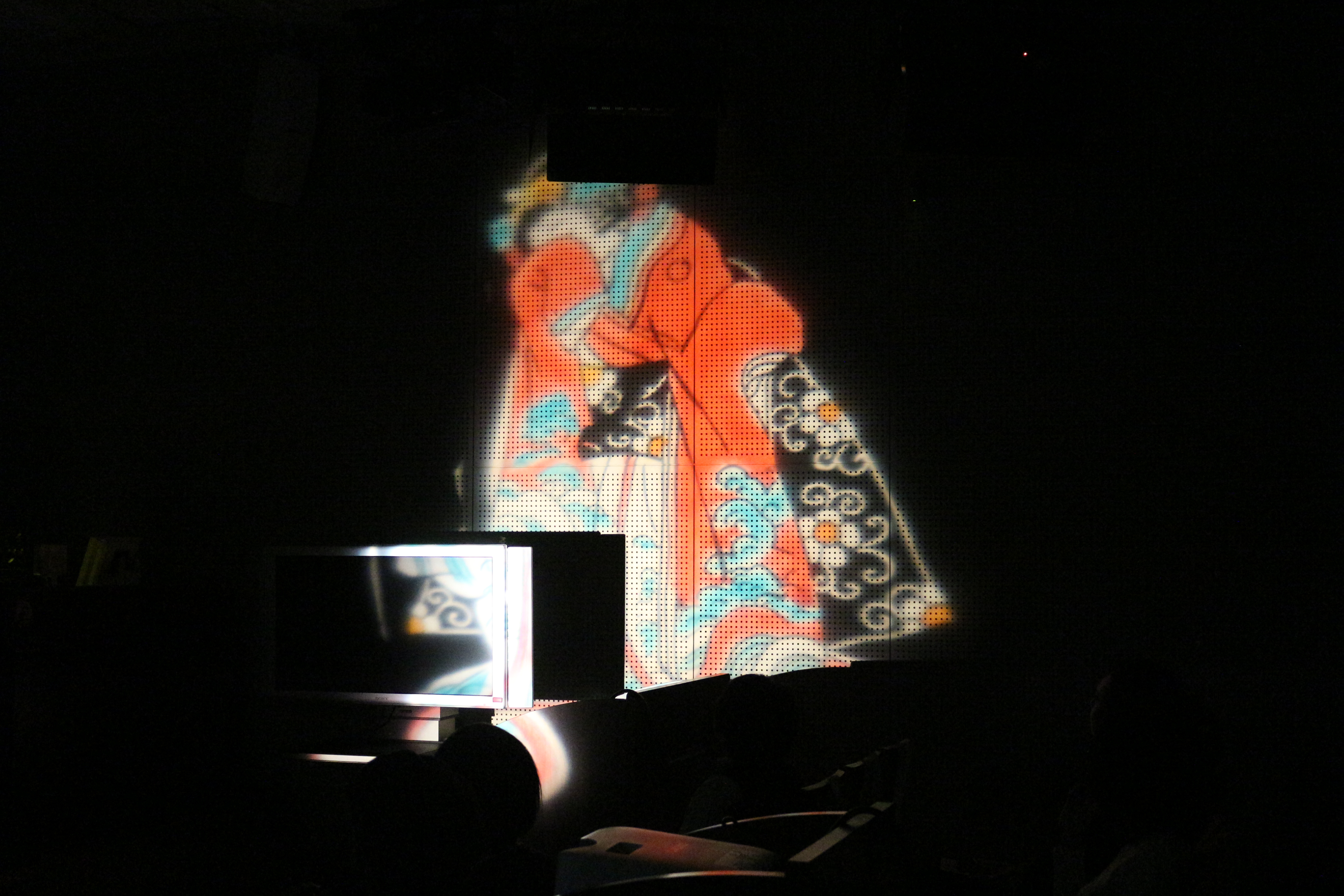
これは「日高川」という作品ですけれども、手持ちの装置でこの会場ならば走り回ることもできるわけです。私の希望で言うと、9割までは完成しているんですけれども、バッテリーを背負うようにするとコードレスになります。そうするとこの装置を持って客席の両方に、例えば花畑をずっと写すことができる。客席が花の中に包まれる、囲まれるような表現ができる。そういうふうな芝居を作りたいと思いまして、まだ部分的にしかできていないですけれども、これから写す人間はスクリーン前とか、それはいろいろ工夫できますけれども、バッテリーを背負ってコードレスで客席を走り回るということを演出的に芝居としてやりたい。そういう世界を描きたい、それが写し絵の魅力なんですね。(会場の壁に独楽の曲芸の写し絵を投影する)

それから、古典作品は時代の精神を映したものです。この種板は西洋にはない縦引きなんですね。西洋のマジックランタンは横に移動しますが、これは縦引きなんです。江戸時代には独楽の曲芸が流行りまして、こういう影響あるんですね。このように写し絵の現代化というのは、そういう(昔の)技術を使いながらやりたい。それからすいません、 会場の明かりをつけてください。
これまでに何度か NHK で写し絵の特集やってくれました。(番組のために)かなり長い時間撮影をしましたが、写し絵の古い作品は、ガラスが割れて使えないものがとても多いんです。それをどのように昔のものを復元するかという時に、うちの美術担当の人間が思いついてマックのパソコンを使って割れた絵の復元をしました。それが成功しました。ここにいる田中がそのやり方を工夫しまして、しっかりと NHK の「写し絵の美術」という特集の中で紹介されました。彼女のおじさんは日本軍から戦争末期に航空写真のカメラを作るように命じられていた人であり、ジブリ美術館にある飛行機を作った。彼女のお兄さんは物理学の朝永先生の弟子、そういうような一家だそうで、全くセンスのない私にとっては表現にとっては助けになったということです。なので、みんわ座は古典作品をそのまま上演し、その一方では現代化ということ取り入れ発展させなきゃいけないと思っています。
草原 面白いと思うのは、風呂がモバイルであるということですね。木で軽くて体で動かせる。今になって、それこそピコプロジェクターとかワイヤレスなプロジェクターとかモバイルなプロジェクターができているわけですけれども、そういう意味では写し絵や錦影絵は、それ以前からモバイルだったわけですよね。
池田 今日映像でお見せした演目のなかで、男が回転するシーンがありました。その種板を持ってきています。いかに本当にモバイル性を利用して動いているかということ、それから回転する仕掛けがありますので、実際に少し演じてもらいます。(会場に錦影絵を投影)
草原 これは花輪車と同じ仕掛けですか?
池田 花輪車は、2枚の輪が軸なしで重なって回る。それに対して、これは1枚です。一枚の回転する仕掛けです。
草原 先ほどフータモさんが(基調報告の中で)、西欧にベルトでお腹につけて演じる幻燈があるというのを紹介していましたが、あれは実は長時間は無理なんですよね。金属なので、長時間投影したら低温火傷どころではなく、高温火傷になってしまう。これは桐だからこそできる。
池田 もう一つ先ほど、「間」「遊び」の話が出ましたが、その遊びみたいな仕掛けを使っているのが錦影絵の「腹揺れ」のシーンなので、そこを見てください。(三番叟を演じる男の腹が左右に細かく揺れる仕掛けを投影)

これはアメリカのニューオリンズで演じた時も、本当に会場爆笑と言うか、太った人が多いところだからだと思うのですが、アメリカではすごい爆笑でした。山形さんもおっしゃりましたが、私たちがイギリスでやった時も、アメリカのボストン、ニューオリンズでやった時も本当にダイレクトに反応してくれて、スタンディングオベーションになるというのは、演じていても気持ちがいい。しかも演じていてスクリーンの裏でちゃんとお客さんの反応がわかる、それを操演に反応させてまたやるという、浸透膜のような和紙(のスクリーン)の存在も、表現にとっては非常に大きいなと改めて思いました。
フータモ ここにいる皆さんはこの考えを共有していると思いますが、私は写し絵というのは単なる過去に対するノスタルジーではないと思います。それは過去から興味深い要素をインスピレーションとして受け取り、そして様々な時代の異なる瞬間の対話を形作っているのだと思います。様々な時代というのは、未来を含めています。ですから、過去と現在と未来の対話が、このような芸術の形態に繋がってるのだと思います。
これはまさに私が研究しているメディア・アルケオロジー、メディア考古学という分野と同様のことだと思います。2年前に私がNTT出版から刊行した初めての日本語の書籍『メディア考古学』の副題は「過去と現在と未来の対話」というものでした。それこそが、写し絵や錦影絵の伝統の中で生じていることだと思います。ですから、この伝統がこれからも存続してさらに今後発展していくことを祈っていますし、日本人によってもっと評価されるようになることを祈っております。
山形 これは願望なんですが、来年の3月久しぶりに公演をしたいと計画していますので、そのうちみんわ座のホームページに載せたいと思っています。見たら是非とも足を運んでください。よろしくお願いします。
草原 付け加えますと、皆さん謙遜しておられますが、池田さんは去年アメリカで公演をされていて、私の映像関係のアメリカの知人達からも素晴らしかったということを随分聞きました。山形さんもみんわ座を率いて、映画研究では非常に有名なトム・ガニングさんに招かれてシカゴで上演とワークショップをやったりとか。それからハリウッドの映画アカデミーだけではなくて、ボストン美術館、スミソニアン博物館、リンカーンセンターという凄い所に招かれて上演している。反響もすごくよかった。そういう影響がアメリカの方からでも出てくるといいですね。
シンポジウム記録・目次
14:00-14:10 開会のことば・趣旨説明
14:10-14:30 共同研究報告「視覚文化史における幻燈の位置」(大久保遼・向後恵里子・遠藤みゆき・上田学)
14:30-14:50 基調報告1 草原真知子(早稲田大学)
14:55-15:40 基調報告2 エルキ・フータモ(UCLA)
15:45-16:00 休憩
16:00-16:25 写し絵上演と解説 劇団みんわ座 山形文雄(みんわ座代表)
16:25-16:50 錦影絵上演と解説 錦影絵池田組 池田光恵(大阪芸術大学)
16:50-17:50 パネルディスカッション「日本のスクリーン・プラクティス」(山形・池田・草原・フータモ)
17:50-18:00 質疑応答・閉会のことば
主催:早稲田大学演劇映像学連携研究拠点 平成29年度公募研究「視覚文化史における幻燈の位置:明治・大正期における幻燈スライドと 諸視覚文化のインターメディアルな影響関係にかんする研究」
共催:早稲田大学文化構想学部表象・メディア論系