平成28年度(2016) 成果報告1
海外大学との連携と人材育成
本拠点では、世界的に知られる優れた演劇関連研究機関と連携を図り、学術資料の共有や共同研究の推進、国際シンポジウムの開催等を通じて人材交流及び若手研究者の育成を推進している。
『沙翁復興―逍遙からNINAGAWAまで』
日本におけるシェイクスピア受容に関する多角的な論考を収めた日英2ヶ国語の展示ブックレット『沙翁復興―逍遙からNINAGAWAまで』を作成した。世界的なシェイクスピア研究の中心であるバーミンガム大学付属シェイクスピア研究所との連携のもと、同研究所のマイケル・ドブソン所長に寄稿していだいたことは特筆すべき栄誉である。
さらに本ブックレットを彩るのは、国内外で活躍するシェイクスピア研究者が日本におけるシェイクスピア受容に関する論考である。岡室美奈子拠点代表の序文に続き、シェイクスピア研究を専門とする東京大学教授・河合祥一郎氏の「現代日本におけるシェイクスピア受容」と本学教授・冬木ひろみ氏「日本のシェイクスピア:翻訳と上演(明治から昭和へ)」、そして拠点副代表の児玉竜一氏による「忘れられたシェイクスピア」を掲載した。日本におけるシェイクスピア受容の歴史と上演と研究の現状をバーミンガム大学の研究者たちと共有できたことで、今後、バーミンガム大学シェイクスピア研究所との連携をより強固なものとし、更なる学術交流を展開する確かな足がかりとなった。
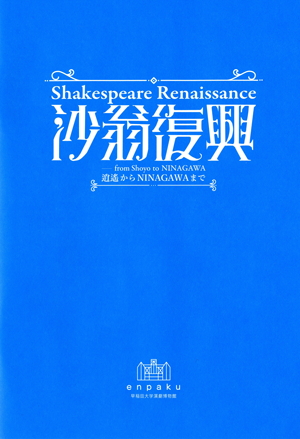
展示ブックレット『沙翁復興――逍遙からNINAGAWAまで』
日仏演劇国際シンポジウム 「越境する 翻訳・翻案・異文化交流」
当拠点の主催により2016年10月25日(火)から27日(木)の3日間にわたって、日仏演劇国際シンポジウムが開催された。当国際シンポジウムは、早稲田大学とストラスブール大学、アルザス・欧州日本学研究所との提携により、2005年度から定期的に開催され、今年度で6回目を数える。言語間の狭義の「翻訳」にとどまらず、演劇、音楽、建築、映画などの様々なメディアを事例に、文化の様々な側面から「越境」のあり方が問われた。早稲田大学国際会議場第2会議室を会場に、フランスから招聘した6名の研究者と国内の若手研究者らによる研究発表をもとに活発な意見交換が行われた。
内外から参集したのべ100人近い参加者は、多くの若手研究者を含む発表者が日々の研究成果を共有し、学際的かつ専門的な国際学会における議論による切磋琢磨を通して、新たな知見が生まれる過程を目の当たりにすることとなった。またストラスブール大学との継続的かつ互恵的な学術交流に支えられたこれらの研究成果を、報告集の刊行によって広く世に問うことができた。当該分野の進展に資するのみならず、「越境」をめぐる問題が喫緊の国際課題となる昨今、その社会的意義は大きい。

2日目のディスカッションより(10月26日、早稲田大学国際会議場第2会議室)
若手研究者海外派遣事業
人材育成の一環として、全国から若手研究者を広く公募し海外での研究発表を促進することを目的とし「若手研究者海外派遣事業」を立ち上げた。本年度は田中里奈氏に対して、国際学会における研究発表のための旅費の一部を助成した。海外の研究所や研究コミュニティとの更なる交流を通じた発展が期待される。
【平成28年度助成内容】
助成対象者:田中里奈(明治大学大学院修士課程)
報告文:2016年9月22日(木)~25日(日)にオーストリア・ヴィーン大学で国際学会Cultural Typhoon in Europeが開催され(テーマ:「東アジアにおける文化的生産の場所(プレイス)と空間(スペース)」)、12か国から諸分野の研究者・アーティストが参加、文化・学問的背景を超えて議論を深めた。報告者は、研究発表「ミュージカルというジャンルにおけるポスト・グローバリゼーション? ―ヴィーン発・日本経由で「進化し続ける」ミュージカル―」を行った。
成果報告書はこちら